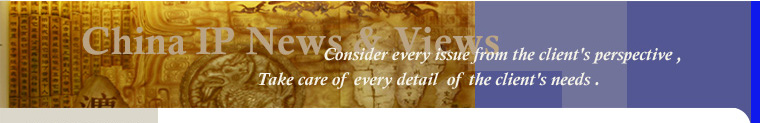|
中国最高人民法院は3月22日午前に記者会見を開き、《専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(二)》(以下、《解釈二》と略称)を4月1日から施行すると通知した。最高人民法院民事裁判第三廷の宋暁明裁判長が《解釈二》に関する状況を紹介した。
宋氏によると、2009年12月、最高人民法院は《専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈》を公布した。専利法の正しい実施を確保し、専利権侵害の判決・決定基準を統一化・具体化し、科学技術イノベーションの専利裁判に対する新たな要請に速やかに応えるため、最高人民法院は専利権侵害の判定基準に関する司法解釈を改めて起草することを決定した。《解釈二》の条文草案は16回にわたる修正を行い、最高人民法院審判委員会の議論を経て、最終的に可決された。
《解釈二》は計31条で、主として請求項の解釈、間接侵害、規格実施による抗弁、合法的出所による抗弁、侵害行為の差止、賠償額の計算、専利無効の侵害訴訟への影響など、専利裁判実務における重点的な難題に関わる。
司法保護を強化し、専利訴訟における「期間が長い、立証が難しい、賠償額が低い」といった顕著な問題の解決に努める。
《解釈二》第21条に定められた専利の間接侵害制度は、専利権者に対する保護を一層強化したもので、現在意見を募集している専利法改正草案にも類似の条文がある。実務において、間接侵害者と発明創造を最終的に実施した侵害者との間に意思疎通がなければ、共同侵害を構成しない。しかし、間接侵害者が自己の提供する部品などが専利権侵害製品に用いることしかできないことを知りながらもなお侵害者に提供した。間接侵害者に明らかに主観的な悪意があり、かつ間接侵害者が提供する部品は直接侵害行為に専ら用いられる物品である、または第三者が専利権侵害行為を実施するよう積極的に誘導したことに鑑み、その行為を権利侵害責任法第9条が規制する範囲に入れた。
宋氏は間接侵害制度について、「現行の法的枠組を超えて専利権者に規定外の保護を与えることを意味するのではなく、権利侵害責任法の適用における然るべき意義であり、専利権者の保護強化という客観的現実に適合する」と述べた。
「立証が難しい、賠償額が低い」という問題について、《解釈二》第27条では、専利権侵害訴訟における賠償額の立証規則に関してある程度の改善を施した。専利権者の初歩的な立証ならびに侵害者の証拠把握状況をもとに、侵害者の利益取得に係る立証義務を侵害者に分配し、それを専利法第65条に定められた賠償額の計算順序と関連付けた。
事件審理期間が長いという問題について、《解釈二》第2条では、「先に提訴却下の決定を下し、別途提訴する」制度を設けた。つまり、専利復審委員会が専利権無効審判の決定を下した後、専利権侵害紛争事件を審理した法院は、行政訴訟の最終結果を待つことなく、「提訴却下」の決定を下すことができ、また「別途提訴」を通じて権利者に司法救済の手段を与えることができる。《解釈二》では、手続上で提訴却下の決定を下すのであって、実体上で訴訟請求棄却の判決を下すわけではないと規定しており、これは無効審判の決定が行政判決・決定によって覆された場合であっても、権利者は別途提訴することができることを意味している。
利益均衡の原則を維持し、権利者の正当な権益を保護するとともに、専利権の不適切な拡張を回避する。
専利法第70条によると、使用者、販売許諾者、販売者による合法的出所による抗弁が成立する場合、その賠償責任を免除することができる。争点は、善良な使用者が合法的出所を証明し、かつ合理的な対価をすでに支払ったという状況で、使用を停止すべきか否かにある。最高人民法院は、検討および関係する立法部門の意見を求めた上で、「専利権の排他性は強いが、無制限に拡張してよいということではない。専利法は専利権者のためだけにある法ではない。専利権者の一方的な利益ばかりを強調し、善良な使用者の正当な利益を顧みることなく、善良な使用者の合理的な空間を占領し、取引の安全を妨害することは、専利法第70条の本来の意図ではなく、利益の均衡を重んじる法律の基本的な精神にも悖る。ゆえに、《解釈二》第25条では、但し書きにより、すでに合理的な対価を支払った善良な使用者の使用停止責任を排除した。つまり、使用者が主観的に善意であり、客観的に合法的出所を提供し、かつ当該侵害製品を取得する際に販売者に合理的な対価を支払ったならば、専利権の禁止力拡大を阻却すべきである」と考えた。
侵害行為差止の判決をめぐる問題に関して、《解釈二》第26条では、「通常、侵害者が権利侵害行為を行い、侵害行為停止の法的責任を負担しなければならない。ただし、侵害者が係争侵害行為を停止することで、国の利益、公共の利益を損なう場合、法院は、係争侵害行為の差止ではなく、合理的な使用費の支払いを命じる判決を下すことができる」と定めた。(出所:人民日報)
|