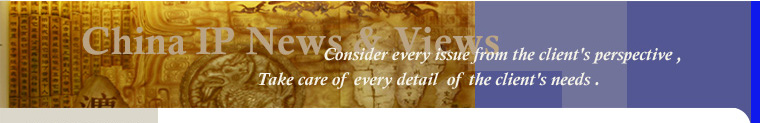|
著作権事件
――ネットワーク上の著作権事件における「役割分担・協力」による作品提供の認定の問題について。裁判過程において主観および客観の2つの面から認定しなければならず、つまり主観上、被告間または被告と訴外者との間に作品を共同で提供する主観的な意思の連絡があり、かつ前述の主観的な意思の連絡を実現するために客観上、相応の行為を実施したか否かを見なければならない。なぜなら主観的な意思の連絡には安定性が存在し、判決の中で被告間に協力の意向の合意がある、行為間に協力または利益の共有などの密接な関係があるなどの事実に基づいて、主観的な意思の連絡の存在を認定することができるが、特定の技術またはビジネスモデルなどの客観的な需要に基づいて確立された「形式上の協力」と区別しなければならないからである。
――画像の著作権の帰属の認定の問題について。先行事件において提訴された権利侵害者が使用した画像が合法的に授権を受けたものであることを証明できず権利侵害が認定され、後続事件においてその権利侵害者がさらに同一画像の著作権者または専用使用権者の身分により原告として訴訟を提起した場合、保存されている証拠に基づいて真摯にかつ慎重に事件の関連の事実を明らかにし、法により当事者に必要な立証指導を行い、保存されている証拠が証明する事実に従って法により判決を下さなければならない。先行事件の有効な判決ですでに明らかにされた事実について、後続事件においてそれを覆すことのできる証拠がある場合、民事訴訟法の関連規定に基づいて法により判決を下す。
――映像作品の著作権事件における当事者の追加の問題について。関連規定によると、共同作品の分割使用が不可能である場合、その著作権は各共同エグゼクティブ・プロデューサーが共同で享有し、協議による合意を通じて行使し、合意することができず、さらに正当な理由がない場合は、いかなる一方も他方による譲渡以外の権利の行使を阻止してはならない。ただし、所得、收益はすべての共同エグゼクティブ・プロデューサーに適正に分配しなければならない。映像作品の著作権が多くの権利者に帰属し、かつ権利者の基本状況を明らかにすることができる場合は、すべての権利者を事件当事者としなければならない。権利者の基本状況を明らかにすることが確かに困難である場合は、裁判効率の向上および著作権者の合法的権利のより良い保護の観点から、その中の1名または一部の権利者を事件当事者とすることができるが、判決文の中に「係争作品のその他著作権者は、係争権利侵害行為により発生した経済損失賠償金の分割を本件原告に主張することができる」など一文を加え、訴訟に参加していない著作権者のために相応の権利を残しておかなければならない。訴訟を提起したのが映像作品の専用使用権者であり、かつその専用使用権が共有著作権者の中の1名または一部の者の権利である場合、その授権がその他著作権者に不適正な損害をもたらすことを証明する証拠が存在しない状況において、その専用使用権者の身分を認定することができる。
その他問題
――民事訴訟法司法解釈第25条の理解と適用の問題について。《最高人民法院関於適用〈中華人民共和国民事訴訟法〉的解釈(〈中華人民共和国民事訴訟法〉の適用に関する最高人民法院の解釈)》第25条では、「情報ネットワーク権利侵害行為の実施地には係争権利侵害行為の実施に使用されたコンピューター等の情報機器の所在地が含まれ、権利侵害結果の発生地には被権利侵害者の住所地が含まれる」と規定されている。高級人民法院立件法廷は北京万象博衆系統集成有限公司が廊坊市徳泰開関設備有限公司、浙江淘宝網絡有限公司を提訴した意匠権侵害紛争事件の二審管轄権の異議の決定の中で、「同条規定における『情報ネットワーク権利侵害行為』は特定の意味を有し、主に情報ネットワークを利用して人身の権益、情報ネットワーク配信権などを侵害する行為をいい、その権利侵害対象である、作品、商標、宣伝内容などはしばしばネットワーク環境下に存在し、ダウンロード、リンクなどのネットワーク行為により発生する」と指摘した。したがって、商標権侵害紛争、意匠権侵害紛争については、関連の係争権利侵害行為は上述の規定における「情報ネットワーク権利侵害行為」ではないことから、上述の規定を適用してはならない。もちろん、この問題についてさらに高級人民法院立件法廷との間で踏み込んだ調整、意思疎通を行う必要があり、具体的な規定が設けられるまでは、最初にこの意見に従って処理しなければならない。
――基層法院が立件した技術契約事件が審理においてコンピューターソフトウェア事件に該当することが分かった場合の処理の問題について。関連規定によると、コンピューターソフトウェアなどの技術に係る民事および行政一審事件は知識産権法院が管轄する。裁判実務において、コンピューターソフトウェアの開発などに係る契約は通常の場合、技術契約の名称が使用されることにより、これに係る紛争は技術契約紛争として基層法院が立件し、その後基層法院が審理過程において契約が実質的にコンピューターソフトウェア契約であることを発見する事態を招く。このような状況について、事件を受理した基層法院は事件の管轄について意見を提起し、高級人民法院民事第三法廷に順を追って報告し、高級人民法院民事第三法廷が統一的に審査を行い、管轄法院を確定する。審査を経て、確かに名称は技術契約であるが実質的にコンピューターソフトウェア契約であると判断された事件は、知識産権法院に送致されその管轄となる。審査を経てなお技術契約であると判断された事件は、事件を受理した基層法院の知的財産権法廷が引き続き審理を行う。
――同一行為について著作権または商標権の侵害を主張しさらに不正競争の構成を主張した場合の処理の問題について。法体系において、通常の場合、反不正当競争法(不正競争防止法)は著作権法、商標法に対して包括的および補足的役割があるとされている。係争行為がすでに著作権または商標権の侵害を構成する行為であると認定されている場合、不正競争防止法第2条などの条項を再度適用して救済することは望ましくない。係争権利侵害行為が多くの行為からなる場合、異なる行為について逐一認定しなければならず、一部の行為が著作権、商標権を侵害し、一部の行為が不正競争を構成する場合、著作権法、商標法および不正競争法を個別に適用して判決を下さなければならない。
――国外送達手続きの問題について。現在の国外送達手続きの複雑性および長期性を踏まえ、国外送達手続きを採用して送達し6か月を過ぎても回答が送達されない場合、同時に公示送達の方式を採用して同一の当事者に送達することができる。
――行政訴訟における新証拠の採用の問題について。行政訴訟において実体上の公正および手続き上の公正を考慮しなければならない。事件の実質的な処理結果に影響を及ぼす可能性のある証拠、当事者の権利の認定に重大な影響を及ぼす証拠および考慮しなければ当事者のその他の救済の機会がなくなる証拠は、証拠の失権について慎重に認定しなければならない。新証拠の採用により社会公共の利益を害さなければ、具体的な事件の状況に基づいて考慮することができる。
――行政訴訟において訴訟に参加すべき第三者が取り消された場合の処理の問題について。商標、専利の権利付与、権利確認に係る行政訴訟において、訴訟に参加すべき第三者が取り消された場合、原則的に行政訴訟法およびその司法解釈ならびに民法通則、会社法などの法律の中の関連規定に基づいて関連の主体を法により追加し訴訟に参加させなければならない。ただし、第一中級人民法院が係争中の事件の処理にあたり実際の困難に直面することを踏まえ、関連の主体の状況を明らかにすることが困難であるまたはその他特殊な状況がある場合、その者を事件当事者としなくてもよいが、取り消された証拠を事後の調査のために記録文書に残しておかなければならない。
――法定賠償の適用および賠償基準の統一の問題について。知的財産権の保護によりイノベーションのインセンティブを図る目的に基づいて、権利侵害の損害賠償はその知的財産権の真の市場価値を十分に反映し、実現しなければならない。保護の範囲、強度とイノベーションによる貢献を互いに適応させ、釣り合わせてこそ、真の意味でイノベーションのインセンティブを図り、創造を奨励することができる。権利侵害訴訟において、当事者、代理人が権利者の損失および権利侵害者の利益獲得状況について立証し、損失および利益獲得状況の明確化に努め、損害賠償計算の科学性および合理性を向上させるよう大いに奨励しなければならない。権利者の損失および権利侵害者の利益獲得状況の明確化が確かに困難である場合、法定賠償金額の確定は知的財産権の真の市場価値を十分に反映、実現し、専利などの科学技術成果に係る知的財産権のイノベーションの程度および貢献度、作品の類型、特徴および独創性の程度、商標の顕著性および知名度、権利侵害行為の性質、権利侵害者の事業規模、納税状況および主観的悪性の程度などと適応していなければならない。同時に、裁量的賠償方法の適用を統一し、適正化する。裁量的賠償は法定賠償ではなく、法定賠償限度額の制限を受けない。市全体の各級法院は法定賠償限度額を超えて裁量的賠償を実施するにあたり、権利者の損失または権利侵害者の利益獲得額がすでに明らかに法定賠償限度額を上回っていることを証明する確実かつ十分な証拠がなければならず、関連事件を処理するにあたっても、高級人民法院民事第三法廷に順を追って報告しなければならない。
――二審で新たに発生する弁護士費、出張旅費などの費用の処理の問題について。《北京市高級人民法院関於確定著作権侵権損害賠償責任的指導意見(著作権侵害の賠償責任の確定に関する北京市高級人民法院の指導意見)》第12条では、「係争権利侵害行為が訴訟期間もなお継続して行われ、原告が一審法廷の弁論終了前に追加賠償の請求を提起し、相応の証拠を提出した場合、訴訟期間内に拡大した原告の損失も併せて賠償範囲に含めなければならない。二審訴訟期間内に拡大した原告の損失も賠償範囲に含める必要がある場合、二審法院は賠償金額について調停を行わなければならず、調停が成立しない場合は、賠償金額について改めて判決を下し、判決文の中で理由を説明することができる」と規定されている。また、第13条では、「本規定第6条第2項における『適正な支出』には次の内容が含まれる。(1)弁護士費、(2)公証費及びその他調査・証拠収集費、(3)会計監査費、(4)交通、食事、宿泊費、(5)訴訟資料印刷作成費、(6)権利者が権利侵害の制止又は訴訟のために支払ったその他適正な支出。上述の支出の合理性及び必要性について審査を行わなければならない」と規定されている。上述の規定を参考にして、当事者が一審訴訟においてすでに弁護士費、出張旅費などの適正な支出について訴訟請求を提起し、二審期間に新たに追加された上述の費用について賠償金額の追加を請求した場合、民事訴訟法司法解釈第328条の「独立した訴訟請求の追加」の状況には該当せず、裁判官は上述の費用の賠償金額について改めて判決を下し、判決文の中で理由を説明することができる。
――判決文の記述書式の簡易化の問題について。知的財産権に係る判決文は事件の具体的状況に基づいて記述を簡易化することができる。ただし、基本的な体裁の統一を保持しなければならず、特に一審判決文では事件の事実の真相およびその証拠、ならびに認定に至った考え方および過程を全面的に明らかにしなければならず、各院は簡易化方式を採用して知的財産権に係る判決文を作成するにあたり、表形式を採用すべきではない。(出所:中国知的財産権ネット)
|